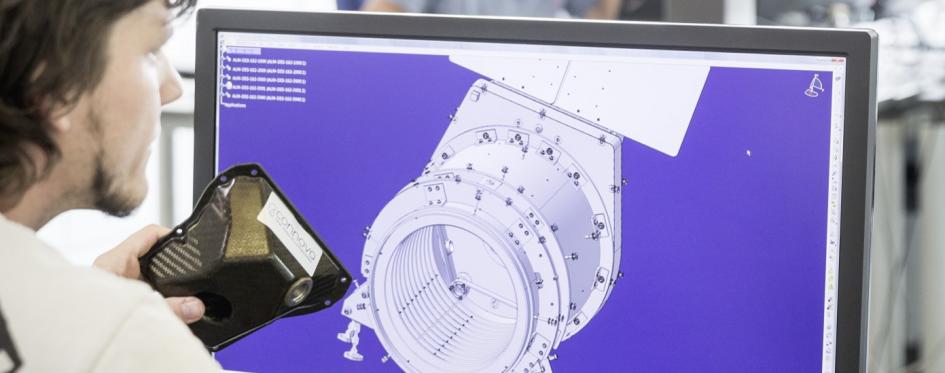1. はじめに
スイスと私との関係は、1998 年から 3 年間ジュネーブに赴任したことに始ま る。通商産業省(現経済産業省)に入省していくつかの産業の政策やエネルギ ー政策を担当したのち、産業政策局大学等連携推進室長として、産学連携政策 に携わった。そして、大学技術移転促進法を制定し終えて、1998 年から 3 年 間、JETROジュネーブ事務所に出向した。そこでは、国際標準化機関のISO、IECの日本の窓口を務めるとともに、WTOの交渉で、日本政府をサポートする役目を担った。また、スイスの産業技術のトレンドなどを調査する業務も行っ た。
今回、その経験を記したスイス大使館のニュースレターでのインタビューが 企業誘致局のご担当の目に留まり、セミナーでの講演を依頼された。記事には、スイスでの経験、特にいかにスイスが優れているかが記されていた。私は帰国後、再び大学連携推進課長として産学連携政策、特に大学発ベンチャー千社計画、MOT(技術経営)一万人計画等を担当し、その後 2006年には(独)新 エネルギー・産業技術総合開発機構に出向、さらに2009年には特許庁審査業務部長に任命され、知的財産政策を含めたイノベーション政策に深くかかわるようになった経験が積み重なった。これを背景に、2012年に早稲田大学理工学術院教授に出向し、大学院生にイノベーション戦略や政策を教えることとなり、2014年の経済産業省退官後に東京工業大学大学院教授に採用され、MOT課程において、本格的にイノベーション政策などの研究教育を担当するようになった。そのイノベーション政策に関する事柄に、スイスでの経験が活かされていたのである。この小文は、この顛末を紹介した先日の講演「日本企業にオー プンイノベーションはなぜ必要か-日本企業とスイスとのイノベーションの共 創」をもとに書き下したものである。
2. 21世紀のイノベーションを巡るパラダイムシフト
イノベーションという言葉は、日本政府の文書では昭和31年の経済白書に 記されたことが初めてといわれているが、このとき、イノベーションを「技術革新」と訳したことが、その後の誤解を生むことになった。イノベーションの 元来の定義は、「様々な資源の結合(新結合)によって生まれた新しい価値、 製品やサービスが社会に価値を創出すること」である。ところが、1990年代まで、日本では「技術の革新」によってもたらされることがすなわちイノベーシ ョンであるとした上で、技術開発を進め、知財を獲得すればイノベーションが進むという印象が世の中に拡散した。基礎研究→応用研究→開発→製造→マー ケティングを経て社会に価値を生ずる(売れる、儲かる)ことがイノベーショ ンのシンプルなモデルであるが、政府内でも企業でも、技術開発に注力すれば、連続的にイノベーションは創成できるとの概念が共有されていた。これは 大きな勘違いで、実社会でイノベーションにたどり着くには、研究開発の最中もその後も、様々な障壁を乗り越えてやっと実現するものであるということが90年代にわかってきた。これは、90年代初めの米国のビジネススクールを中心としてイノベーション研究が発展してきたからである。昨今流行りのオープンイノベーションの概念も、この頃発表された論文が基礎になっている。
さて、イノベーションを巡るパラダイムは、1990年代を境に、大きな変化が見える。最大の環境変化は、デジタル化・ネットワーク化の進展による、「爆発する知識」だ。例えば、学術論文のデータベースから “innovation” に関する論文を抽出すると、2000年代では毎年数千報が確認され、累積では数万報に達する。これは、英語に堪能な研究者でも全部読んで理解するのは相当苦労する量である。さらに、例えば、DNAに関する論文では、1953年のワトソン・ クリックによる DNA のらせん構造の発見を契機に指数関数的に増加し、2000年代には年間10⁵を超える発表があった。これをすべて個人の力で理解するのは不可能な数だろう。現代は研究者にとって苦難の時代と言えるが、それを解決するには新しいツールが必要だ。図1は私の学位論文の一部(i)だが、上述のイノベーションに関する論文の書誌情報(著者、キーワード、要旨など)をもとに、論文の引用関係をあるアルゴリズムによりグラフで表したもので、これを 「学術俯瞰」と呼ぶ。こうすることで、これまでどのように研究が発展し、どの分野の研究が活性化しているかがわかる。最近では、AI(人工 知能)を使って論文の要旨を瞬時に作成できる。今後、研究のトレンドを分析したサーベイ論文の自動作成も可能になると言われている。こうした新しいツールにより、情報爆発時代でも研究や技術開発の方向性を見極めることができる。
3. チェスブロウの提唱するオープンイノベーションとは
シリコンバレーでのテクノロジーマネジメントの経験を経て、当時ハーバードビジネススクールの助教授だったヘンリー・チェスブロウが 2003 年に著し た「Open Innovation」がオープンイノベーションの教科書となっている。本書では、Xeroxとその研究所PARCとの関係、IBM のイノベーションマネジメントの変革などを分析したうえで、クローズドイノベーション・パラダイムとオ ープンイノベーション・パラダイムの違いを説明した。そして、大企業が陥るNIH症候群(Not Invented Here syndrome)を指摘している。これは「自前」主義が企業ではむしろ合理的な行動であり、社外技術の導入はリスク管理の問題をはらみ、またオープンイノベーションはR&Dスタッフの地位の危険をもたらすものであることから、企業がNIHから逃れ難いものだというものである。例えば、IBM のオープンイノベーションは、R&Dスタッフの大規模レイオフという犠牲の後に導入された。さらに、のちの著作では、NSHウィルス(Not Sold Here Virus)も挙げた。事業ユニットが罹るウィルスで、自社で売っていないものは他社でも売れるはずがないとの認識から他社から得た技術の事業化に消極的なるというものである。
米国では、こうした論理的な障壁を乗り越えて、上述のIBMをはじめ、様々な企業がオープンイノベーションを導入してきた。一方、シリコンバレーを中心にバイオ、IT分野で生まれ出てきた大学発のハイテク・スタートアップがオ ープンイノベーションの重要な担い手となってきたとの事実がある。また、80年代以降設立されたスタートアップ、例えばアップル、アマゾン、グーグル、 フェイスブックがその後急成長を遂げ、現在の米国経済をけん引し、世界をリ ードする企業になっていることも周知のことである。これら企業もオープンイ ノベーションを積極的に展開している。
4. 日本企業におけるオープンイノベーションへの対応
1980 年代に日本の自動車、半導体企業等に存在を脅かされた米国企業は大学の研究者とともに日本企業の研究を大掛かりに行い、その中で産学官連携体の存在に気づき、これを「ナショナル・イノベーション・システム」と名付け た。日本では主に国家プロジェクトを中心に、複数の競合する企業が大学、政府研究機関と次世代の研究開発を進めてきた例があり、これを競争力の根源の一つと認識したのである。しかし、米国と違って日本にはハイテク・スタートアップ(あるいは大学発ベンチャー)の勢いはなく、2000年前後になって、政府が、大学技術移転、日本版バイドール条項、そして大学発ベンチャー千社計画などを矢継ぎ早に打ち出したのは、米国のオープンイノベーションとハイテ ク・スタートアップの存在感に影響されたことが大きい。
日本企業は近年オープンイノベーションの必要性を、特に経営幹部が痛感し、経営戦略を担う部署として「オープンイノベーション室」を立ち上げる企業も多数あった。この室長に突然任じられた担当社員は、社長がどこからか聞きつけてきた「オープンイノベーション」なるものの実態とその進め方について一から勉強する羽目になった方も多かっただろう。最近では、本格的にオープンイノベーションに取り組んでいる企業も散見されるが、米国などに比べると、まだ抵抗感が多いように思われる。それを打破するのに有効な手段のひとつが、優れた他国の機関との共創である。
5. スイスとの共創戦略
さて、オープンイノベーションを戦略として持つことが日本企業に必須だとして、日本に足りないものがいくつかを擁しているのがスイスであり、これがスイスの関係機関とオープンイノベーションを進めるメリットとなりうる。
まず、スイスはローザンヌ(EPFL)とチューリヒ(ETH)の連邦工科大学を筆頭に、先端的な研究開発を進め、技術水準は高い。例えばナノマシンテクノロジーについてみると、スイスでは時計産業が独自の発展を遂げてきたが、日本のクォーツ時計の攻勢で壊滅的な打撃を受けた。この時、時計産業が持っていた精密機械の技術を独立した産業として育てる政策を取ったことが、スイスの精密機械産業が大きく飛躍したひとつの引き金だった。その後こうした産業を背景に、先端のナノマシンテクノロジーは EPFLなどで活発に研究され、日本とも共同研究を行ってきた。ナノテクノロジーといえば、その発展のきっか けとなった走査型トンネル電子顕微鏡の発祥の地はチューリヒにある IBMの研究所だ。このように、スイスは大企業の研究開発の拠点にもなっている。ほかにも世界の企業の先端研究所がスイスに集積している。これは、世界の有力 企業の研究開発拠点を誘致しようという国やカントン(州)政府の政策が明確だからでもある。一方、スイスは、物価は高いのに、世界から一流の研究者、 技術者が集まっている。これは、スイスの高い研究開発力もさることながら、 高給取りの技術者が住みたい国として定着したのは、クオリティ・オブ・ライ フの高さゆえといえる。
また、スタートアップ企業は、オープンイノベーションの重要なステークホ ルダーであるが、日本では、大学発ベンチャー育成政策などがやっと機能し始めている段階で、まだ存在は小さいといえる。一方、スイスではチューリヒを中心に、スタートアップ企業の比率が高くなっており、オープンイノベーションの環境が整っている(表1、2)。
こうしたスタートアップを輩出するスイスの大学の研究水準は、 連邦工科大学を筆頭に高いレベルにあり、いくつかの大学評価でも高いランキングにな っている(表3)。産学連携も活発だ。例えば、ETHの傘下には産学連携のための独立組織があり、同学のサイエンスパ ークでは企業と教授、学生が一体になって、共同で技術開発を実施しているのを目の当たりにしたことがある。スタートア ップの設立も盛んで、企業は大学をフルに活用し、大学も企業を抵抗なく受け入れている。他の都市にもイノベーションパークが大学周辺に整備されている。
特筆したいのがスイスとMOT(Management Of Technology、技術経営)の関 係だ。MOTは、企業が、どうやって研究開発から技術開発、そして製品化を成し遂げイノベーションを実現するか、という経営戦略に関する研究と教育のことで、もともと米国のMITのビジネススクールから生まれたと言われている。 経営学であるMBAの中の一分野として1980年代に日本産業の研究などを基礎 に発達してきたものである。欧州ではローザンヌにあるビジネススクールの IMDがこの分野で先行しており、IMDでは技術系出身の社長が学校に赴いて技術戦略を語るなど、実践的な教育が行われている。日本では2000年当時、「日本企業の技術力は高い」と自画自賛していたが、結果として利益率が低いのは、それを製品化して市場に出していく経営戦略が弱いとされる。MOTが有 効な処方箋となりうるのである。一方、MOT教育は、企業から技術のわかる経営経験者を大学に呼んでくればそれで済む、ということではない。IMDなどス イスのビジネススクールの先生は、企業と一緒になって経営戦略を研究し、具体的なケースにも詳しくなっている。日本ではなかなか複数の企業の経営と技術戦略を俯瞰的に見ている学者は少ない。
こうした優れた特性を持つスイスとの共創については、以下を念頭に進めていくことが必要と考える。
① スイスの高い技術水準を活かす
② スイスのグローバルな技術研究開発拠点を活かす
③ スイスの大学の高い水準と産学連携機能を活かす
④ MOTを活かす
⑤ スイスの高いクオリティ・オブ・ライフを享受する
このうち、私が家族とともにジュネーブに滞在した経験から言えば、特に⑤が実際の共創に携わる人材のモチベーションを高めるために最も重要だと感じている。日本企業やそこに働く方々もこの点に注目して新たなオープンイノベー ションの検討を進めることを期待する。
___________
(i) 橋本ほか、「ネットワーク分析によるイノベーションの学術俯瞰とイノベーション政策」 『一橋ビジネスレビュー』 Vol.56, No.4 (2009/Spr.) pp. 194-211 東洋経済新報社
国立大学法人 東京工業大学 教授 博士(工学) 橋本正洋(はしもと・まさひろ)
1980年 東京工業大学工学部生産機械工学科卒業
1982年 同大学院総合理工学研究科修士課程修了
2006年 東京大学工学研究科後期博士課程修了、博士(工学)
1982年 通商産業省入省。産業政策局大学等連携推進室長、商務情報政策局サービス産業課長、NEDO企画調整部長、特許庁審査業務部長等を経る
2012年 早稲田大学理工学術院教授(出向)
2014年 経済産業省退官、東京工業大学イノベーションマネジメント研究科教授に採用。イノベーション政策、知財戦略、知財政策、技術経営を担当
日本知財学会理事・副会長、日本工学アカデミー理事ほか歴任